
『小澤有作文庫』設置と運営にあたって
小沢有作先生が急逝されてから早一年以上の時間が経過してしまいました。大変長いこの一年だった気がしてなりません。
現在、たまり場「ねぎぼうず」およびご自宅にあった小沢先生の蔵書は韓国・ソウル大学校中央図書館に全て寄贈され、あとは目録の完成を待つばかりというところまで来ました。
小沢先生の蔵書が『小澤有作文庫』として韓国のソウル大学校に寄贈されるようになったことは昨年12月8日の「小沢有作先生をしのぶ会」に出席された方々始め多くの方がすでにご存知のことと思います。
今年(2002年)4月無事ソウル大学校へ搬入されたことを皆様にお知らせするとともに、小沢先生の蔵書が韓国へ寄贈されることになった経緯を含めて現状と今後の課題についてご報告いたします。
1はじめに
小沢先生は生前、蔵書を韓国へ寄贈したいと思っていらしたそうです。そのことはまわりのどなたかにお話ししたことがあったかもしれません。それでも多くの人が知らなかったのではないでしょうか。私(高)もその一人でした。
初めて知ったのは昨年8月16日、お通夜当日のことでした。式場で先生の妹さんの長濱ヒサさんにそっと呼び止められました。長濱さんは以前「耳学問の会」でお話しに来てくださった縁で私を覚えていらしたそうです。
「二年ほど前のことだったと思います。ねぎぼうずで報告する機会のとき早く着き兄と二人でした。このとき『有作兄さん、有作兄さんがいなくなったらこの本はどうするのですか』と聞いたんです。そのときはもちろん遺言とかいうことではなかったのですが、兄はにこにこして韓国へ寄贈したいと思っている…と言っていました。韓国には自分の本を必要としている学者がいるから、と。」長濱さんはそのように話されました。
突然のことでそのときは「とりあえず、落ち着いたら折を見て当たってみます」とだけ返事をしたように思います。長濱さんも奥様はじめ、ご遺族とこの件について話し合ってみるとのことでした。
小沢先生があまりにも急に亡くなられたということもありましたが、そのときはただ先生が生前そのようなことを考えておられたということにとても驚きました。次の日、告別式のことです。式の始まる前、再び長濱さんに声をかけられました。「実は昨夜、おねえさん、洋一さん、順一さんに有作兄さんとの会話を伝えました。その結果、韓国へ本を全て贈ることについては全く異存はないとのことです。昨夜遅く韓国から駆けつけた宋珉?さんという方とも今朝方話をしました。韓国へ本を贈るということで、今後のことをお願いしたいのですが」とのことでした。
小沢先生が亡くなられたことだけに打ちのめされていましたが、今後はご遺族の思いを小沢先生の遺志として受け止めて現実を立て直すことから動きださなければならないとこのときから実感するようになりました。
2.ソウル大学への寄贈
とりあえず韓国への具体的な受入先探しから始めました。
宋珉?さんはすぐに韓国へ戻るとのことでしたので、宋さんに当たってみてもらうことにしました。
その後、植民地教育における共同研究でのつながりや「在日朝鮮人教育論」の韓国語訳の出版などでも縁の深いソウル大学校が受け入れ先となってくれないだろうか、ということで宋さんに初めの交渉などをお願いしました。
送る側としても小沢先生の蔵書を韓国へ寄贈するということで、メンバーが必要でしたが、寄贈についてはできればあまり大げさな形で扱われるのはどうも…というご遺族側の思いもあったことから最初は実際に体と時間を使って協力してくれることをお願いできる方にしようと思い志澤小夜子さんに声をかけました。志澤さんは快くその場で引き受けてくださいました。
そのような訳で、志澤小夜子さんと最初に韓国を訪れたのが昨年の9月のことです。
ソウル大学とのコンタクトは全て宋珉?さんが取ってくれました。ソウル大学校師範大学の金基?先生も交えてまず一回目の会合を9月25日にもちました。その席でさまざまな受け入れ先が考えられるが、やはりソウル大学校が一番いいだろうということと、ソウル大学校の中の図書館でも中央図書館がベータベース管理がもっとも行き届いていることや書籍自体の管理についてもいいので師範大学の図書館よりできればソウル大学中央図書館にしてもらった方がいいのではないか、という方向が決まりました。
ただそれもこちら側の意向であって実際に大学側がそのまま受け入れてくれるかどうかもその時点では不明でした。
ソウル大学校でまず私たちが案内されたのは金基?先生の研究室のある師範大学でした。この大学付属の図書館にも案内され、先生方の紹介を受けるとともに中を見学させてもらいました。師範大学学長室にも案内をされ、私たちが今回ソウル大学を訪れた主旨について簡単に宋珉?さんから説明をしてもらいました。学長はなんとか受け入れたいとの意向を示しましたが、実際のところ師範大学の図書館には蔵書を受け入れるスペースがないということでした。二、三年後であれば図書館を新築する予定なので、そのときであればなんとかなるのだが、ということでした。
もし大学の中央図書館の方でその間保管することができれば、その後師範大学へ移転させるということではどうだろうか、ということになりました。
その足で私たちは金基?先生に案内され中央図書館に向かいました。このとき図書館長、司書の方と話し合いの時間を持つことができました。
この時点での私たちの基本的な要望は
・ 「小澤有作文庫」というまとまった形で管理・運営してもらいたい。
・ 日本でも小沢先生の本・資料は必要とされているので、それらの人々を含め文庫は広く一般に公開してもらいたい。
・ 文庫の整理・搬送にあたっての費用をソウル大学の方で負担してもらいたい
の以上の3点にしぼりました。
小沢先生の文献を必要とする人は内外に広く存在していますので私たちとしてはせめて「小澤有作文庫」という形で残してもらって再会したい思いが強くあったことから交渉の大きなテーマとしてそのことを第一に掲げました。
3. 「小澤有作文庫寄贈運営委員会」の発足
日本に帰ってきてから今後の進行・作業等については何らかの「委員会」の発足が必要だと思われ、「小澤有作文庫寄贈運営委員会」を立ち上げることにしました。
メンバーについてはやはり「実際に体と時間を使うことの可能な人」にしようということで最初の立ち上げに佐々木昇一さん、柿沼秀雄さん、大田康弘さん、湯澤和貴さん、遺族を代表してもらって小沢先生の息子さんの小澤洋一さん、また委員会の代表に酒井清治さんに入ってもらうことにしました。韓国との連絡を密に取り合わなければなりませんので、宋さんにも韓国側の代表となってもらいました。
当初、韓国への本の寄贈については「日本においての目録の完成後」ということで進行を練っていましたが、ソウル大学校図書館側からは
・ ソウル大学校としては搬入作業を早急に終えたい―できれば2002年3月まで。
・ 目録作成についてはソウル大学に全面的にまかせてもらいたい(日本側の協力はいらない)。
・ 搬送にかかる費用についてはソウル大学側がもつ
という要望がありました。さらに「たまり場 ねぎぼうず」についてもご遺族側からこのままの維持・管理については1,2年が限度とのことでした。
小沢先生の蔵書の整理についてはその総数を把握することすらその時点では不可能でしたので、目録の完成を待ってからソウル大学への搬送というのはどちらにしても無理なテーマであることが次第に明確となってきました。
とりあえず、ソウル大学への搬送とその後の問題については図書館側と委員会側での協議を重ねていくことで合意を図ることに決定しました。
4. 蔵書の搬入とその後の進行状況
以上のような経過を経て、昨年12月8日の「しのぶ会」には、ソウル大学から金基?先生も出席され、「小澤有作文庫」の贈呈式が行なわれました。
また、今年4月5日には「ねぎぼうず」からの搬出も終え、4月8日にソウル大学中央図書館へ到着しました。
高、志澤の両名はその確認のため、5月24日に再びソウル大学を訪れました。
ソウル大学中央図書館側からは司書の方始め今回の図書の整理に直接関わった人たちが出席しました。搬送後のことからこれまでの報告がまずありました。
・ 本の搬入後、ほこりなどをふきはらい5月末までかかってようやく書架に並べたところ。
・ 本の状況については「単行本」「雑誌類」「資料類」に大きく分類され、単行本(約1万4千冊)についてのデータベース作成作業は2002年12月末までに完成させる予定である。雑誌類についての合本などの整理についてはその後の作業となる。
・ 資料類については分類・整理の予定がない。
・ 「小澤有作文庫」はソウル大学校中央図書館6Fの書庫に設置される。(師範大学附属の図書館ではない)
ソウル大学には「現在では手に入れることのできない貴重な資料が含まれている可能性があるので、分類・整理は無理にしてもとりあえず保管しておいて欲しい」とお願いをしてきましたが、ソウル大学としては今後予算の上でも人材的にも資料を整理し分類するのは無理な状況です。ただ、この分野についての日本側の協力については歓迎するとのことでした。
このとき、解決すべきテーマとして持ち帰ったのが、主に「資料類の分類・整理」をどのようにするか、ということでした。
5. 今後の課題とご協力のお願い
去る9月26日(木)~29日(日)小澤有作文庫寄贈運営委員会メンバー(酒井清治、小澤洋一、志澤小夜子、湯澤和貴、高秀美)5名はソウル大学校中央図書館との資料整理に関する打ち合わせの最終的な会議出席のため、韓国を訪問しました。
初めにソウル大学校中央図書館の担当者から現状について報告がありました。
・ 単行本等、書籍についてのデータ入力は全体の3分の1ほど完成した。今年中に完成の予定だったが、予算の関係上思うように仕事が進まなかった。目録作成も含めいずれにしても2003年6月までは完成する予定である。
・ 定期刊行物等、雑誌などについては合本化することと、テーマごとに検索ができる形をとるよう目録作りの作業をする予定である。
・ 文庫の設置場所については一般閲覧のできる書架ではない(書庫に直接立ち入ることはできない)。寄贈本など貴重本を収容しているフロアになるので本の閲覧については目録が完成した後、その目録にもとづいて申請しその場で閲覧するという形をとる。外への貸し出しはできない。
・ 封筒等に入った資料類については目録をつくる予定はない以上がソウル大学校中央図書館担当者からの報告です。今回の会合テーマの主要な課題は前回の懸案事項であった封筒などに入った資料の保管および分類作業についてでした。
寄贈委員会は前回の訪問時に資料類は保管して欲しい。資料類について目録化する予定がないのであるなら委員会側でサポートする手段を考えるとのことになっていました。
当初図書館側は資料についてはデータベース化することは慣例上ないので作れないとのことでしたが、交渉の結果、小澤有作文庫・資料類というような別枠を設ける形にしましょうというところまでこぎつけました。ただ、これは図書館側がデータベースを作るということではなく、日本側が作ったものを別枠を設けて載せるということです。ですから私たちが作らなくてはなりません。
単行本の目録が完成すれば「小澤有作文庫」の本を閲覧することはできますが、資料類について整理しておかなければ、どのような資料があったのかすら誰も知ることなく埋もれてしまう恐れがあります。
なんとか資料類を保存しデータベース化して残すというところまでソウル大学校中央図書館とこれまで交渉を進めてきましたが、今後は実際に資料を分類する作業が残されています。
蔵書の搬出で運搬費だけはソウル大学校が負担したものの、それ以外の渡航費などにかかる費用はこれまで各委員の自己負担でほとんどを賄ってやってきました。しかし、今後も継続的に委員らの自己負担だけで賄うのは限界であり、カンパを募る他ないとの結論にいたりました。
来年2003年6月までという時間的な制約もあります。その期間内にどれだけできるかわかりませんが、なんとかやれる範囲でやる他はありません。とりあえずは今年の12月末に再度ソウル大学校中央図書館で作業を行う予定です。
今後はできれば広く多くの方々のご協力をいただければ幸いです。特にカンパのご協力をお願いいたします。(ご面倒ですが、銀行振込でお願いします。)
詳細についてのお訊ねは『小澤有作文庫寄贈・運営委員会』までご連絡ください。
2002年11月4日
『小澤有作文庫寄贈運営委員会』
委員 大田 康弘
小澤 洋一
柿沼 秀雄
高 秀 美
酒井 清治
佐々木昇一
志澤小夜子
湯澤 和貴 (五十音順)
連絡先: 〒179-0072 東京都練馬区光が丘7-7-2-1210
湯澤 和貴気付
℡・Fax 03-5968-7363
カンパお振込み先
金融機関 中央労金
支店 一ツ橋
口座名 小澤有作文庫寄贈運営委員会
(オザワユウサクブンコキソウウンエイイインカイ)
普通口座 0822990
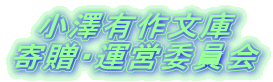
(2002年11月4日)